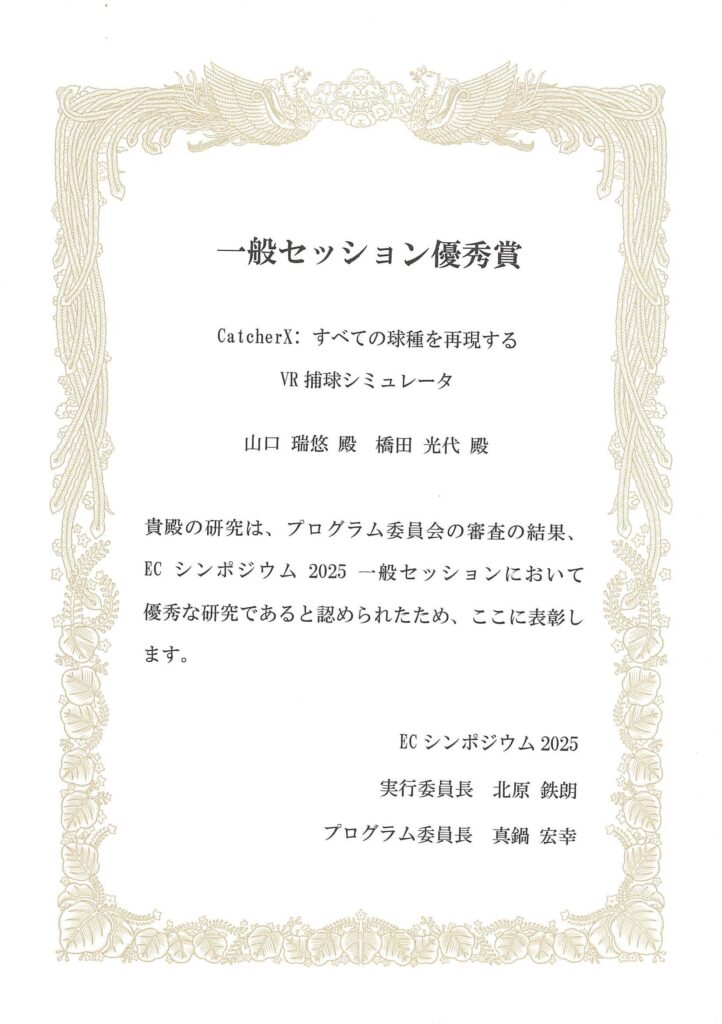2025年8月25日(月)〜27日(水)、「エンタテインメントコンピューティング(EC)シンポジウム2025」(主催:情報処理学会EC研究会)が開催され、本学地域情報学研究科生、情報学部生計4名が3つの賞を受賞しました。
ECシンポジウムは、エンタテインメントコンピューティング(EC)に関連する新技術や新たな可能性、ECと人・社会とのかかわりをテーマとした学術会議で、2003年から毎年開催されています。23回目となる今回のシンポジウムは、「EC is borderless」をテーマに、日本大学 文理学部キャンパス(東京都世田谷区)で開催されました。
一般セッション優秀賞
『CatcherX: すべての球種を再現するVR捕球シミュレータ』
情報学部2年生 山口 瑞悠さん(橋田光代研究室)️
●山口 瑞悠さんの受賞コメント
今回,一般セッション優秀賞を頂くことができ,大変光栄です。
本システムは、既存のVR 野球コンテンツが打撃や投手の体験に偏り、捕手として能動的にボールを捕りに行く体験が欠如しているという課題を補うことを目的としています。その第一弾として,捕手の視点で投手が投げる球を受けるVR シミュレータを制作しました。野球を愛する私自身が、従来のコンテンツに物足りなさを感じ、「捕手としての守備を体感できる環境を作りたい」という強い思いから始めたプロジェクトです。
まだ道半ばではありますが、この受賞は今後の開発に大きな自信を与えるとともに、捕手視点に特化した改善を着実に重ねていく動機づけとなりました。捕球動作やリード、配球、投球の多様性など、捕手だけでも追究すべき要素は数多く残されており、さらなる精度向上とリアリティの追求に取り組んでいきます。
最後に、制作および発表の各段階でご助言・ご協力をくださった皆様、そして指導教員の橋田光代先生に、深く感謝申し上げます。今回の受賞は、多くの支援のおかげで成し得たものです。
レコメンデモ認定(デモ・ポスター発表に関する専門委員推薦賞)
※今回は、デモ・ポスター枠に投稿された86件の発表の中から、10件が「レコメンデモ」に選ばれました。
『ホラーゲームにおける行動特性を考慮した動的なプレイヤ誘導モデルの開発』
情報学部4年生 若林 一稀さん、地域情報学研究科2年生 川西 凜乃助さん(両名とも藤井叙人研究室)

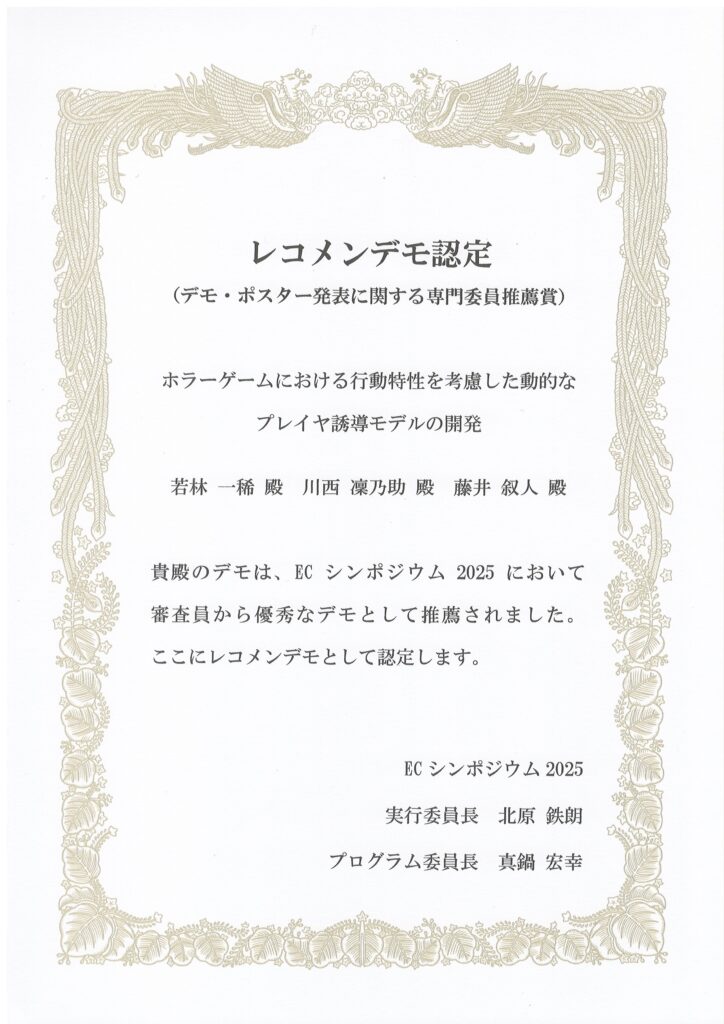
●若林 一稀さんの受賞コメント
ECシンポジウム2025において、提案システムのデモ発表をレコメンデモに推薦及び認定いただけたこと、心より嬉しく思います。
本研究はホラーゲームにおける誘導をプレイヤごとに最適なものにし、ゲーム体験の質を低下させないことを目的としています。講評では,映像や書籍にはなくゲーム特有の課題に注目した点や、数値を用いたモデルを具体的に提示している点などに言及いただきました。今後は、今回の発表経験や頂いた助言を基に、より一層研究開発に邁進してまいります。
最後に、ECシンポジウム2025での発表は、研究開発活動に関わってくださった皆様のご尽力により実現したものであります。論文執筆からデモ発表のサポートに至るまで、熱心なご指導をいただいた藤井叙人先生に感謝の意を表します。 また、福知山公立大学のゼミ生には実験にご協力いただきましたこと、心より御礼申し上げます。
STORES賞(スポンサー企業による選奨)
『ProjectDAWIY – GriCo:Excel VBAを用いた確率的自動作曲システム』
情報学部1年生 山崎 承太郎さん(橋田光代研究室)

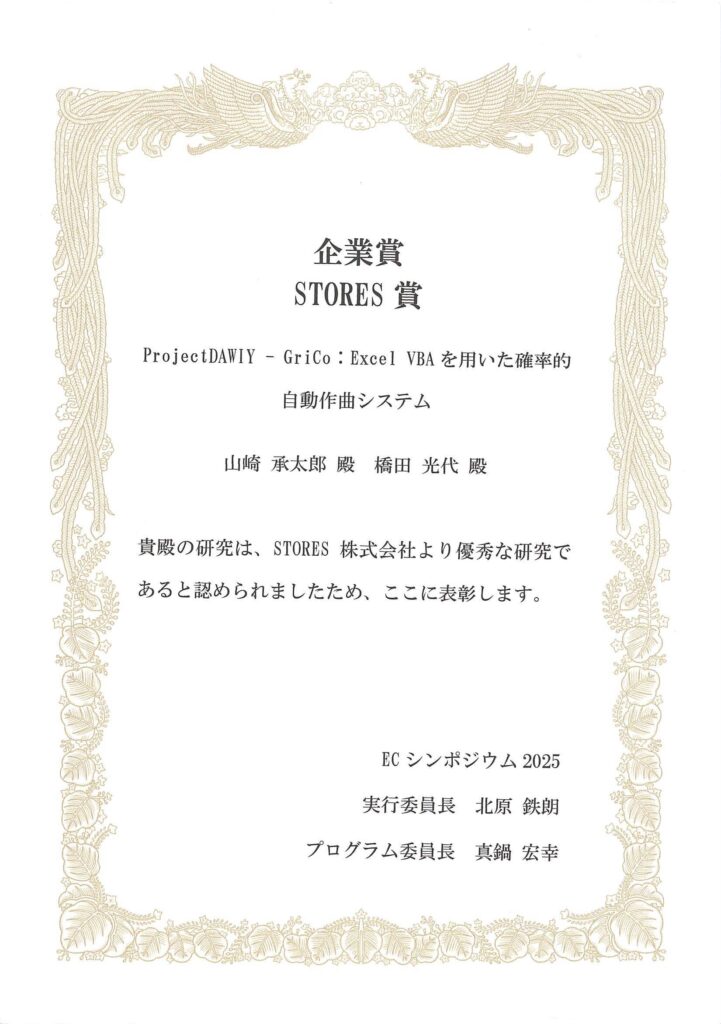
●山崎 承太郎さんの受賞コメント
STORES 株式会社様より企業賞をいただくことができ、本当に嬉しい気持ちと、私の研究を評価いただいたことに対するありがたさで胸がいっぱいです。
私が今回発表した研究内容の要点は、大きく分けて2 つあります。1 つ目は、確率を用いたメロディの自動生成システムの開発を通して、多くの人が未だ聴いたことのない、それでいて聴きたくなるような楽曲を制作することです。そして2 つ目は、作曲家個々人に合わせて音楽制作環境を自由にカスタマイズできるプラットフォームの構築を目指す、というものです。
私の音楽制作に対する様々な感情が起点となり始まったこれらの研究ですが、達成したいことのまだほんの少ししか実現できていないと感じています。表彰の際にいただいたコメントや、発表時に色々な先生方、企業の方々がくださった貴重なご意見を参考にして、今後はより目標に実直に、妥協せずに開発を進めていければと考えています。
そして、今回の受賞は、そこに至るまでの論文執筆、ポスターの作成、発表スライドの作成、その他あらゆる面において、ゼミ担当教員の橋田光代先生や、ゼミの先輩、またそれ以外にも研究開発に関わってくださった沢山の方々のご協力があったからこそ、成し得たものであると感じています。皆様に深く感謝の意を表します。本当に、ありがとうございます。