西田 豊明 副学長

- 専門分野
- 人工知能、会話情報学
| 最終学歴 | 京都大学大学院工学研究科博士課程中途退学 |
|---|---|
| 学位 | 京都大学工学博士 |
| 自己紹介 | 1954年京都府船井郡八木町(今の南丹市)の生まれです。父の転勤に伴い、浜松市、堺市に住み、大阪府立三国ケ丘高等学校を経て1973年に京都大学工学部情報工学科に入学しました。電気工学か情報工学か迷ったのですが、大きな可能性を秘めたコンピュータに取り組むのがチャレンジに満ちていて面白そうだったので、日本で初めて設立された情報工学科を選びました。入学後も、結局一番未知領域に見えたAIに進み、研究課題を見つけて、手探りで成果を出して論文発表しながら大学教員になりました。プロフェッションでは、奈良先端科学技術大学院大学の設立時の初代教授の一人になり、その後、東京大学、京都大学を経て福知山公立大学の情報学部の立ち上げのお手伝いをし、初代学部長になりました。三十代半ばくらいまではある程度想定された路線を進んでいましたが、その後は思いがけず訪れた転機で冒険側を選び、思いもかけぬ面白い人生を歩んでいます。 |
|---|
- 座右の銘
- 自由奔放
| 研究の キーワード | コモングラウンド |
|---|---|
| 研究の概要 | 学生の時からAIの研究をしてきました。自分のパートナーとなって知的活動を助けてくれるAIをつくりたい、というのが出発点でした。その後、言語理解、定性推論、知識共有、そしていま取り組んでいる会話情報学と少しずつ研究の焦点を変えていきました。現在は、人と人ばかりでなく人とAIの円滑で依拠できるコミュニケーションの基盤となるコモングラウンドを可知化して、テクノロジーで強化する研究に取り組んでいます。現在のアプローチでは、会話を、その背後にあるコモングラウンドを構築し発展させていくアクティビティとして定義することで、たとえば会話の成功とはコモングラウンドの構築と発展がうまく進むことであるという具合に、見通しよく研究を進めていくことができると考えています。これにより、我々にとって最も身近にあるコミュニケーション手段であるにもかかわらず、必ずしも意思疎通がうまくいくとは限らない会話の円滑さと信頼度を飛躍的に高めて超会話を実現するテクノロジーを作り出したいと思っています。 |
| 研究テーマ |
|
| 所属学会 | 人工知能学会、AAAI、IEEE、情報処理学会、電子情報通信学会 |
|---|---|
| 研究シーズ(相談可能な領域) | AIや会話を中心にした研究開発コンサルテーションをいたします。 |
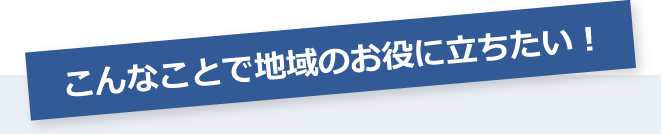
強い冒険心を持ち続けて、不思議の国を築こう。
