倉本 到 教授

- 専門分野
- エンタテインメントコンピューティング(EC)、ヒューマンエージェント/ロボットインタラクション(HAI/HRI)、ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)
- 主な担当科目(学部)
- 統計学、コンピュータプログラミング、エンタテインメント情報学
- 主な担当科目(研究科)
- 人間情報技術特論、地域情報学特別講義、インターンシップ
- 研究室ページ
- https://itarukuramoto.wordpress.com/
| 最終学歴 | 大阪大学大学院基礎工学研究科情報数理系専攻博士後期課程修了 |
|---|---|
| 学位 | 博士(工学)大阪大学 |
| 自己紹介 | 転居の多い子供時代の後、学部4年を飛び級して大学院へ。院生時代は声優を追って全国をめぐり、テレビ局から取材を受けた。2001年、国立大学法人京都工芸繊維大学助手。同大学助教、准教授を経て、2017年大阪大学基礎工学部特任准教授。2019年より現職。2010年からはラジオパーソナリティとしても活動。趣味は国内外のビール。謎検1級。楽しいことが大好きで、楽しさを世の中に拡大するような研究を継続的に行っています。コンピュータによる楽しさを地域社会の活性化に貢献できればよいと考えています。 |
|---|
- 座右の銘
- なさぬ善よりなす偽善
| 研究の キーワード | ゲーミフィケーション、ロボット対話システムと応用、擬人化エージェント、インタラクションデザイン |
|---|---|
| 研究の概要 | 計算機技術の発展に伴って、コンピュータは人間の作業を単に肩代わり・自動化するためだけでなく、人間の生活や生き方を豊かにするために利用することができるようになってきました。私の研究では、コンピュータの持つ能力を人間の豊かさの拡大に利用することを目指しています。具体的には、ロボット・対話エージェントと人間との関係性を構築する技術や、コンピュータが人間を楽しませる・心地よく感じさせる・気持ちよく活動させるための技術の開発と評価を行っています。 |
| 研究テーマ |
|
| 所属学会 | 情報処理学会、ヒューマンインタフェース学会、芸術科学会、ACM |
|---|---|
| 研究シーズ(相談可能な領域) |
|
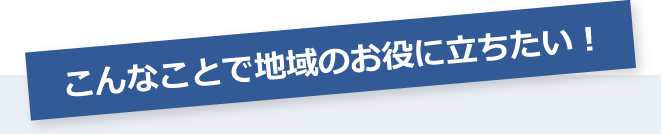
コンピュータやロボットを使って世の中を幸せにする技術は、必ずしも派手で大げさなものだけではなく、ちょっとしたシステムで雰囲気や環境をぐっと良くできることもあります。それには場面に合った技術やアイデアを相談しながら決めていくプロセスが重要です。これから地域のことを学びつつ頑張りますので、ぜひお気軽にお声をかけていただき、大学発の情報技術を地域で活用していただければ嬉しく思います。
